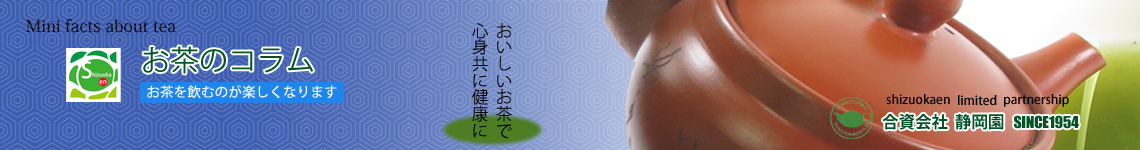
初めてのお客様で「クレジットカード決済」をご利用される方は是非一度こちらをご覧下さい。 クレジット決済 ご購入案内 よくあるご質問
お茶に関する素朴な疑問 (お茶のコラムNo3)
お客様から寄せられたお茶に関する素朴な疑問の話あれこれです。軽く読み流していただければ幸いに思います。宜しくお願いします。
お茶の生産について

お茶はツバキ科の常緑樹です。茶の樹は10月頃になると白い花を咲かせます、やがて花が散り残された子房は毛に覆われて越冬し、春とともに成長して夏頃には成熟した種子になります。しかし茶栽培では葉 以外に栄養分の消費を防ぐために花や実をつけさせません。葉が摘み取られるのは1年に3回くらいで一番茶では4月の下旬から5月中旬頃まで、二番茶ではその後40~50日後の6月下旬から7月上旬に伸びた新葉を摘み、3番茶は更に30~40日後の8月初旬頃摘みます。 苗木から育てて一人前の茶園になるまで約5年かかります。茶の樹が威勢のいいのは7年~10年くらいです。茶樹は施肥したり雑草を取ったり敷き草をして防寒対策し大事に育てられます。一番茶の芽生えの頃は良く霜の被害が有ります。風のない晴れた日の明け方に良くあります。その為防霜対策として防霜ファンが取り付けられています。
【茶の栽培の北限について】
チャはもともと原産地が亜熱帯ですので寒さには通常弱い植物です。お茶の栽培が経済ベースで採算がとれる北限は太平洋側は茨城県大子町と日本海側は新潟県村上市を結んだ線が北限になります。栽培の北限は青森県黒石市になります。
【一番茶、二番茶とは】
茶の樹の冬期は休眠状態になっていますが寒い時期を通り過ぎる3月頃になると気温の上昇と共に茶芽がふくらみ伸びてきます。そして黄緑色の新芽が伸びて一葉、二葉と開き始めてきます。静岡県では4月下旬~5月上旬にかけて摘採されるのが「一番茶」です。一番茶を収穫した後2週間位してまた新しい新芽が出てきます。一番茶の収穫後45日ぐらいで「二番茶」がとれます。品質の面では「一番茶」の方が上になります。秋から冬の冬眠期を経て樹の中に十分蓄えていた栄養分が一気に「一番茶」の新芽の為に消費されるからです。うま味の成分のテアニンが「二番茶」の3倍以上有りますのでおいしいわけです。お値段も「一番茶」の方が高いです。二番茶は短期間で急成長するため一番茶ほど「うま味」の成分は少ないですが盛んな太陽の熱を浴びて成長するのでカテキンとかタンニンが多く含まれています。
静岡茶について
【静岡茶はなぜ優れているか】

静岡県の茶園の面積は17,100ha(日本全体の40%)で荒茶生産量は30,800t(日本全体の38%)で茶の生産はダントツです。もともとチャの樹は亜熱帯原産で温暖な気候を好みます。しかし極端に暑い地域では茶の生産が多いですが品質が極端に落ちます。かたや寒冷地での生産はもともと亜熱帯原産のチャの樹にとっては寒さに弱く凍霜害を受けやすく生産が安定しません。チャの樹の栽培に適した処は年平均気温が14~16℃の範囲で冬の最低気温が-5℃程度に収まる処とされています。また年間の降水量が1,500mm以上で特に3月~10月の生育期間に1,000mm以上必要とされています。これらの条件の気温と降水量とも静岡県の一部を除いて殆ど当てはまっています。静岡県は気象の面でも優位な立地条件になっています。また静岡県は茶の栽培の歴史が長く今まで多くの人たちが築いてきた優れた栽培技術のノウハウや多くの優秀な栽培管理の機械や製茶機械のメーカーが有ります。また荒茶の仕上げ加工業者が約600社もあり全国に向けての一大集散基地となっています。
【静岡でも紅茶作っている】
日本で紅茶が作られたのは明治7年(1874年)でした。その頃は生糸とともに重要な輸出品でした。世界の需要はその頃緑茶から紅茶に移りつつ有りました。当時日本政府は中国人技術者をよんで国産紅茶の製造の指導に当たらせました。それから輸出用に紅茶は生産されるようになりましたが、もともと日本の紅茶原料の茶葉は中国種の系統で紅茶の原料には向かない品種でした。かたやインドやセイロンの紅茶原料はアッサム種という品種で紅色が濃く香りの非常に強い茶葉で日本の紅茶より優れ太刀打ちできませんでした。そこで日本政府は日本に適した紅茶の原料のための品種の開発をはじめました。昭和10年頃に「べにほまれ」という優良品種ができました。その後中国種とアッサム種を交配して「べにひかり」、「べにふうき」など育成されましたが昭和30年代には8,500トンも生産されましたが海外との価格競争に敗れ、昭和40年代の半ばで終わりました。現在少しですが国産紅茶として生産消費されています。
