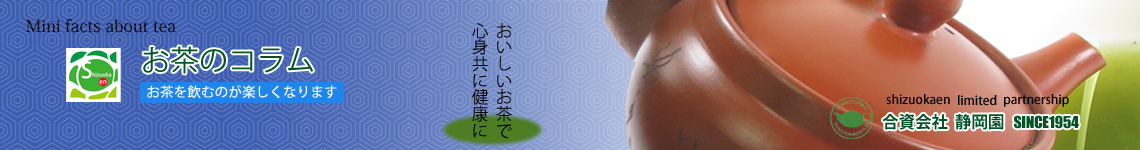お茶に関する素朴な疑問 (お茶のコラムNo4)
お客様から寄せられたお茶に関する素朴な疑問の話あれこれです。軽く読み流していただければ幸いに思います。宜しくお願いします。
お茶の気象
【茶の凍霜害について】

茶の樹の原産地は亜熱帯です。従ってもともと寒さには弱い性質があります。日本で栽培するのには気候とうまく向き合っていかなければ被害が出ます。茶芽の耐寒性は厳寒期はそれなりにあり、-6℃くらいは耐えられますが、春から新芽が発達して水分を多く含むようになるとだんだん寒さに弱くなり-2℃で凍霜害を受けます。日本の上空に寒気が流れ込み高気圧が覆い、風のない朝方には放射冷却現象がおこり非常に冷たい霜が新芽や茶葉におります。霜に当たった新芽は組織が壊死して茶色に変色していまいます。もちろんお茶の品質の低下は免れません。そのために冷たい空気を撹拌するために茶畑の各隅には大型の防霜ファンが設置されています。
【チャの気象災害】
チャの気象災害には寒害、凍霜害、干害、湿害、雪害、潮風害など有ります。干害は雨が降らない水不足で、湿害は長雨などで排水が悪い場合、根腐れを起こす事などです。潮風害とは台風の通過などで非常に強い潮風が吹き続くことで葉が傷んだり塩害が発生することです。主に九州から東海の沿岸部で起きることがあります。また最近は温暖化の影響で長期間雨の降らない干害が頻繁に起こるようになりました。チャの樹にとって一番深刻なのは凍霜害です。一番茶の摘採の直前に低気圧が通り過ぎた後、寒冷な高気圧に覆われると発生しやすくなります。凍霜害は-2℃以下になると発生して新芽が壊死して枯れてしまいます。この時期夜間に晴れて雲がなく、風が弱い時はチャにとって大変危険なサインです。だいたい八十八夜を過ぎると遅霜の被害はなくなります。
凍霜害を防ぐ方法には、茶樹を被覆する被覆法、大型の扇風機で風をおこす送風法、茶樹に水をまく散水氷結法が有ります。この中でも現在一番普及しているのは「送風法」です。1970年代にミカン園で実用化されていた「防霜ファン」を茶園用に改良されて全国に広まっていきました。防霜ファンが上層の暖かい空気を吹き下ろすことにより、茶株面付近に出来た冷たい空気の層を撹拌して温度を上げます。防霜に一番効果のある散水氷結法は茶葉を氷で包み0℃以下にならないようにする方法ですが、大量の水の確保や排水設備の確保などむずかしい課題が多く、あまり普及していません。
【誘蛾灯による害虫駆除】

茶の樹にもいろんな害虫がつきます。2種類に分けられます。1つは新芽を食害して生葉の収量や品質に直接影響を与える害虫、もう1つは成葉や根を食害したり、樹液を吸って樹勢を弱らせたりする害虫です。その中でも前者の蛾など仲間を捕獲殺虫するために「誘蛾灯」を茶畑に設置します。虫の光に集まる性質を利用し、蛾などの害虫を誘い寄せて駆除します。特に夏の夜になると街灯の光に虫が群がっているのをよく見ますが、誘蛾灯はこのような虫の性質を利用して虫を捕獲し殺虫する機械です。蛾やカメムシなどの夜行性の虫は照明光に吸い寄せられるように集まります。虫が光源に向かっていくこの習性は、走光性と呼ばれ、誘蛾灯もランプの光によって虫を誘引し捕獲します。虫が感じる光の波長域は250~400nm(紫外領域)。人間の可視光は400~700nmなので虫は人間に見えない紫外線を色として認識しているのです。